![知られざる東南アジアの発酵食品の世界。ミャンマーは発酵食品の先進国!?[東南アジア、ミャンマー]](https://ceresmom.jp/wp-content/uploads/2018/04/myanmarhakko.jpg)
日本でも昔から馴染み深い納豆やお漬物、味噌や醤油などの食品。これらは全て発酵食品ですよね。私が住んでいるミャンマーでも、多くの種類の発酵食品が日常的に食べられています。
そのなかには、なんと日本のものとそっくりな納豆や、様々な食材を漬物にしたものがあります。
日本やミャンマーで身近な存在である発酵食品には、すごいパワーがあるのをご存知ですか?
今回は、知られざる発酵食品のパワーと、実は日本と近い食文化を持つミャンマーの発酵食品事情をご紹介します!

日本でも身近な発酵食品のスゴさとは?
「発酵」とは、微生物の持つ酵素によって食品のでんぷん質やタンパク質を分解され、酵素やアミノ酸などの人間の身体にとって有益な物質を作り出すことです。
食品を発酵させることにより、下記のようなメリットがもたらされます。
発酵させることのメリットその1・食品の旨味が増す
発酵させることにより、元の食材にはなかった豊かな香りが生み出されたり、深い味わいに変化したりします。
発酵させることのメリットその2・栄養価が高まる
発酵にすることで、元々食品が持っている栄養成分が変化し栄養ががアップします。また様々な研究により、発酵食品を摂取し続けることで、風邪やアレルギー、過敏性腸症候群などのお腹の不調などの症状を抑える効果があることもわかっています。
発酵させることのメリットその3・保存性が向上する
昔から馴染みのある発酵食品は、現代のように冷蔵庫が普及していなかった時代にも重宝されました。食品を発酵すると菌の働きによって保存できる期間が長くなります。
ミャンマーにも発酵食品がたくさんある?!

私はミャンマーの田舎町に住んでいて、毎日のようにミャンマーの家庭料理を食べています。すると、日本以上に発酵食品が多いことに驚きました。
まだまだミャンマーの田舎では電気の供給が不安定で、冷蔵庫を持っている家庭は多くありません。
そのため冷蔵保存ができないので、常温で長期保存ができる発酵食品が多く食べられているのです。
日本の納豆そっくりな発酵食品がミャンマーにも!

ミャンマーのなかでも、私が住んでいるシャン州の市場では見た目が日本の納豆と同じような大豆の発酵食品があります。匂いもまさに日本の納豆そのもの!
どちらも見た目は同じですが、その発酵方法は少し異なります。日本では水戸納豆に代表される稲ワラに包んで発酵させる方法が一般的です。ですが、ミャンマーでは稲ワラではなく、バナナの葉やシダの葉などに2,3日包み発酵させます。
シャン州に住んでいるミャンマー人にとって、この納豆はとてもポピュラーな食べ物でこちらでは納豆そのままを食べるだけでなく、煮る・焼く・炒めるなど様々な調理方法で食べられています。
また、生の納豆を潰して乾燥させた加工食品も多く出回っています。納豆が平たく加工されたものは、焼いて油と一緒にご飯のお供にしたり、小さく丸められたものはスープや炒め物など様々な料理に砕いて使われます。

大豆を発酵した納豆は生でもある程度の保存性があります。これをさらに乾燥し加工することで、その保存期間は2倍3倍にもなるのです。
日本では生の納豆とご飯を一緒に食べるのが一般的ですが、ミャンマーで初めて食べた様々な納豆料理は納豆を食べ慣れた日本人の私にとっても馴染みやすい味です。納豆の入ったスープや焼いた納豆は想像がつきませんでしたが、ミャンマーで食べられている納豆料理のバリエーションに感心しました。
日本の味噌のような存在の「ンガピ」

ミャンマー人が大好きなミャンマー料理に使われる調味料があります。それは、魚やエビなどを発酵させて作る「ンガピ」と呼ばれる塩辛いペースト状のもの。「ンガピ」の匂いはとても魚臭く、日本人にとっては強烈な匂いかもしれません。ですが、料理に入れると魚のコクが料理の味を引き立て、とても味わい深いものになるのです。ミャンマー料理の定番であるカレーや煮込み料理、スープやサラダなどどんな料理にもこの「ンガピ」は使われます。日本の味噌のような存在で、ミャンマー料理には欠かせない発酵食品なのです。
まだまだある!ミャンマーの発酵食品

ミャンマー料理をよく見てみると、そこにはたくさんの発酵食品があることに気づきます。ミャンマーの家庭に必ずあるラペットウは、お茶の葉っぱを発酵させたもの。
「ラペットウ」はミャンマーでは驚くほどの万能食品で、おかずとしてももちろん食べるし、ご飯とラペットウを混ぜて食べる「ラペッタミン」という混ぜご飯もミャンマー人はみんな大好き。トマトや玉ねぎなどと混ぜてサラダにもなり、ピーナッツや干しえびなどを添えてお茶請けやお酒のつまみとしても食べられます。
他にも、豆腐を発酵させて唐辛子のペーストと食べる日本では沖縄料理として知られる豆腐ように似た発酵食品や、ソーセージなどのお肉の発酵食品もあります。日本よりも酸味の強い葉物野菜や人参、大根などの漬物は、ミャンマーでは麺料理に添えられて食べられることが多いです。
ミャンマーの発酵食品事情、いかがでしたでしょうか?
冷蔵保存が一般的ではないミャンマーには、長期保存が可能な多くの発酵食品が重宝されています。
日本の納豆と同じような発酵食品が、様々な調理法で食べられていたり、知らない発酵食品の世界がまだまだあるのですね。
※実は伝統的な製法で作られた日本のお酢も「発酵食品」って知っていました? 無農薬栽培のお米を使って作られた飯尾醸造の富士酢についてこちらの記事で詳しくご紹介しています。
最新情報をお届けします
Twitter でセレスマムをフォローしよう!
Follow @ceresmomjp![ミャンマーの有機農業事情と、私たちがミャンマーでオーガニックを重要視する理由とは?[東南アジア、ミャンマー]](https://ceresmom.jp/wp-content/uploads/2018/02/myanmaryuki.jpg)
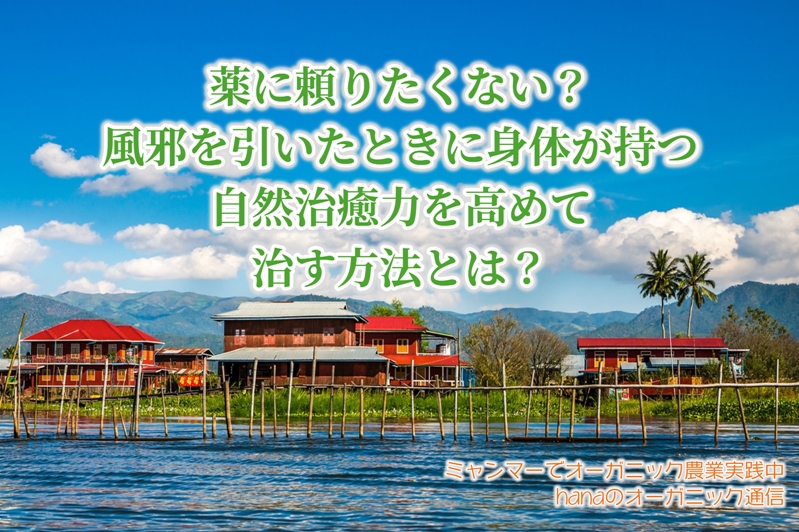
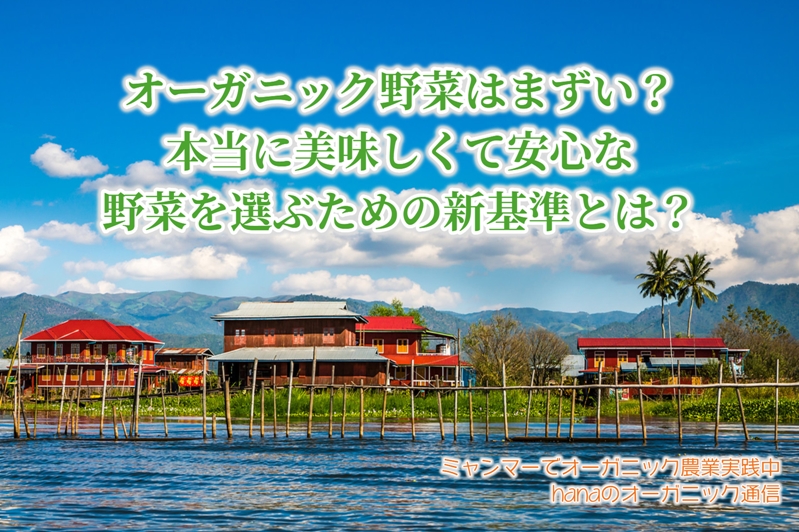
![知られざる東南アジアの発酵食品の世界。ミャンマーは発酵食品の先進国!?[東南アジア、ミャンマー]](https://ceresmom.jp/wp-content/uploads/2018/04/tunaconfy.jpg)
![知られざる東南アジアの発酵食品の世界。ミャンマーは発酵食品の先進国!?[東南アジア、ミャンマー]](https://ceresmom.jp/wp-content/uploads/2018/04/tsukushi-1.jpg)
フェイスブックでコメントする